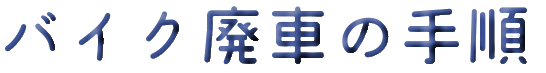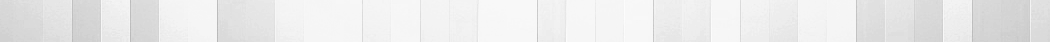普通車とは手続きが違う軽自動車c
軽自動車は、同じ4輪車でありながら普通乗用車とはかなり法的手続きに違いがあります。
もともと排気量の小さい軽自動車は「自動車の小型版」というよりも「バイクを大型にしたもの」というふうな取り扱いがされてきているため、自動車税の支払い先も普通乗用車のように国宛ではなく、登録をした地方自治体になります。
しかも支払い義務のある税金の額は普通乗用車に較べてかなり安く設定されており、現在のような長期的な不況になってくると普段乗りに使う車には普通乗用車よりも軽自動車の方が多くの人に選ばれるようになるのもわかります。
現在国際競走の影響で軽自動車についてそのような税制上の取り扱いをもっと普通乗用車に近いものにしようという政府の動きもありますが、軽自動車の大手メーカースズキの会長兼社長である鈴木修氏が「弱い者いじめ」と表現したように、大きな反発を招いています。
長年「一般市民が気軽に乗ることのできる車」を作ってきたスズキ社長だからこそ、安易に税金を引き上げようという役人の考えには腹が立つのでしょうね。
廃車手続きの種類
ところで軽自動車の廃車手続きについてですが、こちらは3種類の方法から選ぶことができます。
・自動車検査証返納届(一時使用中止)
・解体返納
・解体届出
この3つからなっており、廃車にしたい軽自動車の現在の状態とそれ以降の取り扱いをどうするかによって処分方法が異なってきます。
まず最初の「自動車検査証返納届」は、一時的に自動車の使用を止めるという場合に行います。
軽自動車は登録をすることでナンバープレートが発行され、その番号にもとづいて車検や自動車税の支払いなどをしていくことになります。
そこで一時使用を中止する届出をすることでそうした支払い義務もなくなり、公道を走ることもできなくなります。
車検期間が残っていても切り捨てとなり、再度登録をする場合には残り期間は加味されずあらたに行わなくてはならなくなります。
次の「解体返納」ですが、これはもうその軽自動車を使用しないことがわかっているときに行います。
指定業者から「解体届出書」を発行してもらい、それとともにナンバープレートを返納して処理は終わります。
最後の「解体届出」は、最初の自動車検査証返納届で一時的に中止していた軽自動車を解体処分するときに行います。
指定業者から「解体届出書」を発行してもらい、それを自治体の受付窓口に提出することにより、二度とその軽自動車は再使用できなくなります。