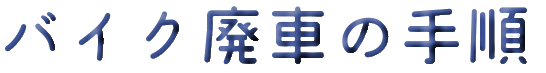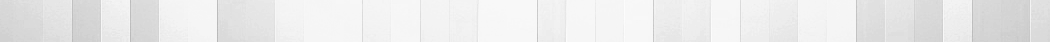あおり運転とは
故意に周囲の車両に対して、不安をあおるような接近やクラクションの乱発などの危険行為や妨害行為です。
必要以上に車間距離を詰めたり、車と車の間にバイクを滑り込ませるなども、相手が恐怖を感じたことで「あおり運転」と認識されるので注意が必要です。
自動車やバイクだけでなく、自転車もあおり運転に対象となりました。
優良ドライバーやバイカーにすれば信じられないことばかりですが、それだけ交通ルールを守らない人が増えたということです。
バイクにも増えているあおり運転
あおり運転は罰則化されるようになったものの、街中では「あおり運転じゃないかな」というようなシーンを目にすることもあります。
平成元年5月、石川県白山市の北陸自動車道でバイクによる事故が発生しました。
この事故で大型バイクに乗っていた男性が死亡、並走者による事故として加害者は過失運転致死容疑で書類送検されました。
ところが、1年後に「あおり運転による事故」であることが判明したのです。
後続車のドラレコからは、無理やりな車線変更や追い越しする車の姿が残っています。加害者は「車線変更しようと思ったらバイクが加速してぶつかった」といっていますが、ほんの少しのことが大きな事故に繋がってしまいます。
バイクは加速する乗り物なので、あおられやすく事故に巻き込まれると大けがだけではすまなくなるケースも少なくありません。
事故に巻き込まれないためにも、あおり運転の対処法を頭にいれておきましょう。
あおり運転の対処法
バイクの場合、車のように窓を閉めてロックし通報できません。
公道で「あおり運転にあったかも」と感じたら、できるだけ人の多い場所にバイクを駐車しましょう。
一般道であれば警察署や交番があれば立ち寄り、ガソリンスタンドやコンビニなど人が多い場所を選んで、相手が暴言や暴力をふるってきた時に目撃者となる人が必ずいるようにします。
高速道路であれば、非常電話スペースパーキングエリアやサービスエリアでやり過ごしましょう。
コンビニの駐車場であれば、防犯カメラもありますので何かあった時の証拠として有効になります。
身の危険を感じたら、すぐに110番に通報してください。車のナンバーや車種などが分かればそれを伝えて対処してもらいます。
ドライブレコーダーも有効
どんな時でも、自分の身を守るためには車間距離には余裕を持たせ、誤解されないように運転することも大切です。
また、バイクのドライブレコーダーの普及率は低いですが、安全や証拠を残しておくためにも有効な手段です。
バイクにステッカーを貼って、あおり運転を寄せ付けないようにするなど、あらゆる対処法で自分の身を守りましょう。