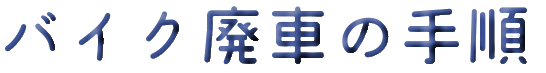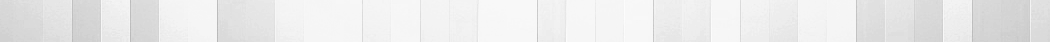日本のバイクはいつ登場したのか
現在でこそバイクは日本全国、また、世界各国に普及しています。
しかし昔は、バイクの存在しない時代がありました。
バイクが初めて考案されたのは1860年ごろで、フランスの発明家によるアイデアでした。
そこから1880年代に、ダイムラー社という企業がバイクのエンジンを開発しました。
さらに1903年にアメリカのウィリアム・ハーレーとアーサー・ダビッドソンにより、現在のバイクに近い乗り物が作り出されました。
そして1920年頃には、現在のバイクに近い製品が生産されるようになったのです。
これがバイクの始まりです。
このように、バイクが最初に考案・開発されたのは海外です。
バイクの情報は日本にも広まり、日本で「国産バイクを開発したい」という人が現れるようになりました。
国産のバイクは明治41年に登場しました。
このバイクは「NS号」と名付けられ、島津楢蔵氏という人物が設計しました。
島津氏はバイクに憧れていましたが、当時のバイクは大型の輸入製品であることから、非常に高級なものでした。
そのため島津氏は、「国産で、購入しやすいバイクを作りたい」という思いから、NS号を開発したのです。
NS号の登場により、バイクが普及するようになる
NS号は、およそ396ccの排気量をもっていました。
これは現在でいう中型バイクに相当するサイズです。
島津氏はバイクに憧れていましたが、当時はまだ20歳という非常に若い年齢でした。
当時はすでに大きな企業が存在しており、車などの機械製品を開発していました。
しかし島津氏はバイクに対する熱い思いのみで、大企業に勝る製品を作り上げたのです。
島津氏は、貴金属の加工業を営む家に生まれました。
そのため島津氏はものづくりに関する知識を、ある程度ですが持ち合わせていました。
ただ、バイクに関する知識は当然まったく持ち合わせておらず、海外からさまざまな資料などを入手して、試行錯誤を重ねてバイクを開発したのです。
まさに島津氏の強い情熱が、日本のバイクを生み出したのです。
ここから日本ではバイクが量産されるようになりました。
大手企業がバイクに注目するようになり、「宮田製作所」という企業が大正2年に「アサヒ号」というバイクを開発しました。
NS号のような排気量はなく、175ccのサイズでしたが、量産型のバイクとして国内初の製品でした。
アサヒ号が普及するようになると、年月を重ねるごとに新しいバイクが次々に発売されるようになりました。
日本のバイクが世界へ輸出されるようになる
こうしてバイクは現在に至るまで改良が重ねられ、国産バイクは海外からも評価されるようになりました。
現在では、日本のバイクは世界各国に輸出されており、最初から輸出を想定したバイクも開発されています。
日本のバイクには、このような歴史があるのです。